
『チェッキネッロ:アルベジアーノのお陰で、全データ即時アクセス可能になった』
★3月16日(日)、アルゼンチンGPモトGP決勝でのホンダ選手のリザルトは以下のとおり。
6位ヨハン・ザルコ(ホンダLCR)
9位ジョアン・ミール(ホンダファクトリー)
10位ルーカ・マリーニ(ホンダファクトリー)
18位ソムキャット・チャントラ(ホンダLCR)
※アイ・オグラ失格により、ザルコ以外の選手は順位が1つ繰り上がった。
★決勝後、ホンダLCRのルーチョ・チェッキネッロ(チームマネージャー)が次のように話した。
[ 中編はこちら ]
【今年1月からロマーノ・アルベジアーノがテクニカルディレクターを務めているが…】
「具体的な作業内容は分かりませんが、うちとファクトリーチームのコミュニケーションや選手間のコミュニケーションを改善してくれてます。
まず、そこから着手してたようで、うちとしては実に良かったですよ。全データへの即時アクセスが可能となり、そのうえ、各情報や将来的な開発についても共有できるようになったんでね。
今はベストな作業計画や、内部コミュニケーションの最適化を練ってくれているところで…やはり、これまでの経験から優先すべき点を、ホンダ側に指示しているようです。」
【ところで、アプリリアが欠場選手のために事前モトGP機テストの提案をしているが…どう思う?】
「全面的に理に適っていることだし、私は賛成です。実際、それが必要な選手がいるのだし…(復帰したての)選手を危険にさらすようなことは、ちょっとねぇ…。
ただ、留意すべき提案ではあるが、必要があるからと言って規則をころころ変えるわけにはいかないでしょう。コンセプトは良いが、来年に向けて検討すべきことなんじゃないんですか。
まぁ、こう言う言い方をしたら、マッシモ・リヴォラ(アプリリアレーシングCEO)は面白くないだろうけれど…ただ、私は全体的な方針のことを言ってるんですよ。
どこのメーカーであれ、特定のメーカーの利害に関わる度に規則を変えるなんてことをしたら…悪い前例になってしまうでしょ。
とにかく、マッシモの言ってることは正しいし、これまで取りこぼしていた案件ですからね…ただし、規則を変えるのは2026年に向けてでしょうね。」
[ 完結編に続く ]
(参照サイト:『Gpone』)
(Photo:Instagram)
(2026/01/08 22:52:50時点 Amazon調べ-詳細)

























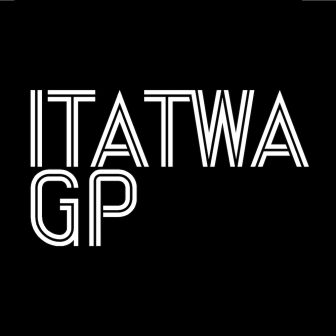
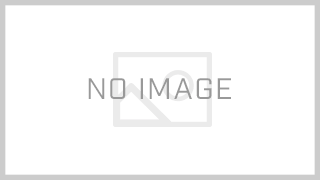



















具体的な作業内容は分かりませんが、うちとファクトリーチームのコミュニケーションや選手間のコミュニケーションを改善してくれてます。
コレがなんで出来なかったのホンダさんって言いたいですね。外部からの人で日本人以外だったから言えた様に思う。
日本人のスタッフは、思っていても言えない雰囲気がホンダのチーム全体にあった。
本当の問題点は各部署全体でのコミュニケーション不足が目には見えないが雰囲気も含めてだった。私は責任はアルベルト プーチと日本人のスタッフの責任感の弱さが次に来ていたと思っています。
〉全データへの即時アクセスが可能
おぉ、ホンダは改善したか!
ヤマハの体制状況はどうか?
逆に言えば彼が来るまでその程度の事すら満足に出来なかったのか… そりゃあ何年も同じ問題を抱え続けた筈だわ
うーん…クラッチローが居た時はふつうにしてたよね?
クラッチローが「マルクのデータ見てる俺は彼がどれだけすごいことしてるか分かる」ってよく言ってたし
それが自由なアクセスかはともかく最新パーツも先にクラッチローが試してたじゃん
どうして昔できてたことができなくなっちゃったんだろうね
第三者から見てもダメだったところがやっと改善。
外から圧力ないとダメなのね。
> 全データへの即時アクセスが可能となり
今までしていなかったことがただただ驚きです。
サテライトチームに情報共有しないのは企業の姿勢として当たり前だと思うけどねぇ?そう思わない人が多いのに逆に驚いてます。同じメーカー下でも異なるチームで切磋琢磨していくのが正しい気もするし。事実最近ではグレシーニでさえ他のメーカーに鞍替えしているわけだし。今の改善は今までのやり方のホンダが実現した改善なのかもしれないよね?このデータの開放が後に改悪になる可能性もあるわけで、、、まぁ期間限定なら良いのでは?と思います。エスパルガロがホンダに加入した当時に話していたように、ホンダは他のメーカーがしていることを聞いてこなかったとの事、この姿勢がホンダの良さでしょう?
プーチの責任というより長期体制の弊害だろうね
ライダー出身のプーチと技術屋のアルベジアーノでは着目点も違うだろうし、近年はエンジン、フレーム以外の進化が大きいからもっとはやく体制の見直しが必要だった
データ共有化なんかはほんの一部で色んな面で風通しがよくなったんやろうね
かつてのサテライトチームはレース参戦の数合わせみたいな扱いだったけど、今はどのメーカーでもサテライトチームと上手く連携しないと取り残される時代
オールドタイプの人は理解できないかもねぇ…
昔はデータどころかタイヤも差別してたからなあ
日本メーカーはそれでも勝ててたからその慣例が抜けにくかったのか?
ホンダも211V時代は今のドカみたいにホンダカップ状態だったんだし
海外メーカーはドカなんか数十年以上勝てなかったから出し抜く為のやり方でしょ、エアロ及びサス制御よろしく
SBKだと当然のように差別してたしな
単純にサンプルデータは多ければ多いほど、確率が上がって良いのが当たり前で、やっとそれに気づいたホンダの遅さってだけで、それを良さと考えるのは相当難しいなー。
どうも数での勝利が好きな方が多いみたいですね。ヒーローより数で勝のは好みではないなぁ・・・。
過去はワークスチーム同士の戦いの層とサテライトチームの戦いの層という階層があってこのピラミッド構造がコストの面や選手や開発多様性や成長に機能していたのだけど、平均値をとればとるほどワークスの意味がなくなっていく。
この仕組みはどうしても勝てないDUCATIがサテライトを巻き込んだ数の戦いに持ち込んでデータの少ない分野、日本勢が手を出さない製品に反映の困難なエアロやライドハイドなど各種機能を持ち込み優位に立ったわけだけど、これ、結局のところ失敗するよね。唯一の救いはMARCがDUCATI入りしてくれたことでその失敗が解りづらくなったことくらいかなぁ。
ファクトリー以外のチームが
ただグリッドの賑やかしではなく戦闘力を持つのは
IRTA(国際ロードレーシングチーム協会)会長が推し進めていたことです
IRTA会長のエルベ・ポンシャラルはテック3のオーナーでもありますが
現在苦境に立たされてるとはいえKTMに参加したのはそういった理念のためです
サテライトは自らの意思でより良い条件のメーカーを選んでいます
DUCATIが一時期8台を走らせていたのはドゥカティが強要したわけではなく
サテライトが自分から移動した結果です
サテライトをファクトリーと比べ軽視するのはそこに参加するスポンサーやスタッフの侮辱と一緒です
過去ペッコが「昔はサテライトとファクトリーに戦闘力の差があって安全だった」という旨の発言をした時に
ポンシャラルが怒ったのはファクトリーライダーがサテライトを下に見て驕ったような発言をしたからです
サテライトは賑やかしではありません
失敗するというのはどういう失敗のことですか?
レースで考えれば結果が全てですが、それ以外の話を言ってるのですよね?
レースの勝敗でしか考えられないとその競技は衰退しますよ?
よく結果がすべてといいますが、その結果も現在の結果でしかないならねぇ。 今強いDUCATIも今回の2025プロトを採用しなかった時点で今のDUCATIのデータ共有による皆の平均点手法では上限がみえてきているのかもしれない。結果今後は特定の選手向けの車両を作るしかなくなるでしょうね。2025車のチームメイトとの差はすでにそれが起こっているのかもしれないですよ? 話は変わりますが、私は選手が腕上がり対策の「改造手術」をしなければならない時点で終わっていると思っています。MOTOGPクラスは撤廃しMOTO2クラスを変わりに当てて行くのが筋だと思います。WSBKはうまくやっているなぁと思います。欠点はプロトタイプ車が走らない事なのでそこだけ許可し、ライドハイド・エアロ・ECU共通化など市販車に不要なものは排除するべきです。 ヨーロッパ勢に有利条件を進めた事が今の事態を招いています。逆に路面センサーやアクティブサスペンションなどは取り入れてよいと思います。
なるほどです。ドゥカティは「エース専用のバイク」から「誰でも乗れるバイク」へ転換して成功を収めましたが、GP24でその戦略が限界に達しているという視点ですね。
確かに、エース専用機に頼りすぎると、エースが不調になった際にはホンダのように低迷するリスクがあります。もしドゥカティがマルケス専用機にシフトすれば、歴史は繰り返される可能性があり、その点ではすでに危うい方向に向かっているのかもしれません。
MotoGPがプロトタイプクラスとしてWSBKとの差別化を図っている以上、Moto2のような仕様への移行は魅力を損なうリスクがあり、実現は難しい気がします。ただ、自分も「マシンの差より個人の技術の差を見たい」という点には共感するので、2027年からの技術規制の変化は、tamさんが指摘する方向性に沿うものになることを期待したいですね。
また、ライドハイドが許容されている現状を踏まえれば、「路面センサー」や「アクティブサス」の方が、レースを技術の実験場とするMotoGPの本来の趣旨に合っているという意見にも賛成です。
いや、エースが不調は書き方悪かったです。
マルケスは限界超えたり、後追いまでして必死に走ってエース級の走りは継続してました。
でもホンダはエース専用機がまともに走れなくなると、専用機方向に振ってたからロレンソすら対応できず低迷して行った。ですね。
ホンダも一時はダニ仕様とマルケス仕様があったのですが、ホンダとしては新世代のライダーが皆マルケスの様になるように仕様を1本に絞ったのか?なんて思ってもみますが(中上選手がそこそこ乗れたような気もした)実際はお金の問題なんでしょうねぇ。